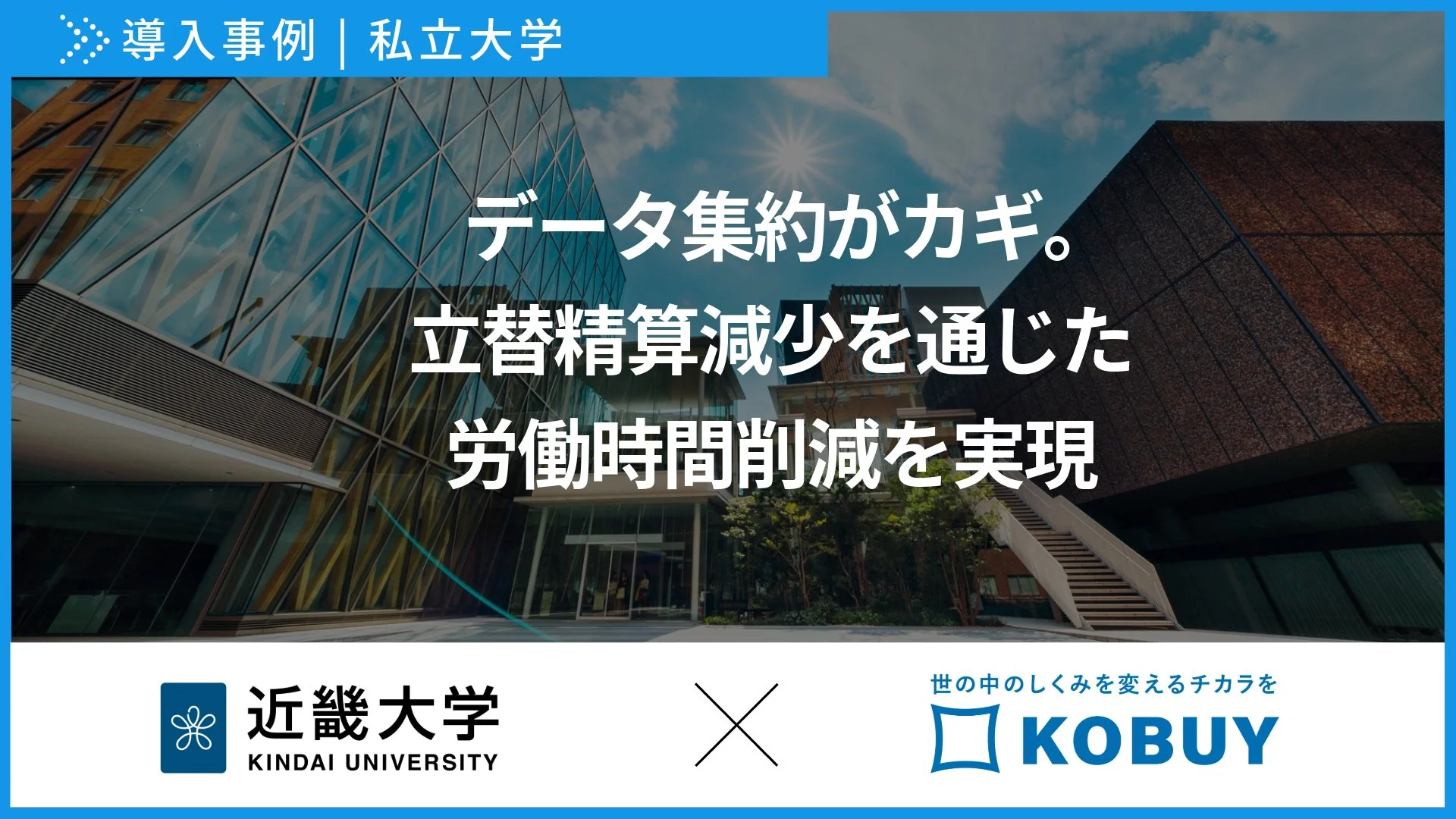【KOBUY 導入事例 近畿大学 学術研究支援部 様】
今回は、KOBUYを導入いただきました近畿大学の事例をご紹介いたします。
大学における予算管理と適正な運用は、コンプライアンス上重要な問題です。同時に、近畿大学が考える大学の競争力を支える「研究の機動力」も両立させなければなりません。
今回は、近畿大学 大学運営本部 学術研究支援部 補助金事務課の杉田晃一課長に、KOBUY導入による問題解決について、お話をうかがいました。
ビデオインタビューを見る
大学校費と研究費の違い
大学で研究を行う上での予算は2種類あり、性格や取り扱い、対象となる教員に違いがあります。この点について、杉田さんに解説頂きました。
杉田さん
「教員が使える予算のうち『大学校費』は、各部門や用途単位の予算として管理している教育・研究・部門運営などに使われる、職員も使う予算です。
一方で『研究費』と呼ばれているものは、学術研究支援部が管理している予算となります。こちらは、国や企業から研究費を獲得した人が使える予算となり、教職員全員が利用できるわけではありません」(杉田さん)
そのため、使える予算として見た時に、大学校費は専任職員全員に割り振るが、研究費は使える教員ごとに紐付けなければなりません。そのため、予算と教員との紐付け作業が煩雑になります。
Amazonは絶対、という教員の強い声
近畿大学でKOBUY導入のプロジェクトが立ち上がるなかで、特に学術研究支援部における課題は、「Amazonを使いたい」という教員のニーズへの対応と、「立替精算を減らしたい」という課題解決を両立することでした。
杉田さん
「商品の取りそろえや納品までの時間短縮から、教員には研究費におけるAmazon利用のニーズが大きくありました。しかしKOBUY以前のシステムや申請方法の中でAmazonを利用する場合、教員による立替払いになっていました。
立替払いをするには、立替払い理由書を書き、領収書を添付した上で、通常の物品購入のための申請が必要となります。添付する書類が増えてしまい、確認作業が増加してしまいます。教員も学術研究支援部も、お互いに時間を余計に使わなければなりません。
同時に、先生に先にお金を負担してもらうことになり、個人のAmazonアカウントでの購入は、私物と研究費での購入の区別がつきにくくなるなど、不正の温床にもなりかねません」(杉田さん)
購入申請は、学内システムによるデジタル申請となり、領収書などは添付ファイルでの扱いが可能ですが、監査の対応のために原本の提出が必要となるため、教員に提出してもらった上で、紙の管理が増えることになります。
Amazon利用へのニーズが高まる中、厳格な運用をしようとすると教員・職員双方で非常に大きく工数が増える立替払い。外部研究費(科研費)の支出は、科研費だけでも年間5000件にも上りますが、そのうちの3割に相当する1530件が立替払いとなっており、これを大幅に減らすことが、KOBUYに寄せられた期待でした。
データ集約がカギに
教員のAmazon利用のニーズが高く、独自に利用してきた実態がある中で、KOBUYを経由したAmazon利用は、学術研究支援部に、立替精算を減らすための条件となっていました。その実態から明らかになった問題点もまた、存在していました。
杉田さん
「教員の中には、すでに大学のメールアドレスで独自にAmazonのアカウントを作って、個人用として利用している人が多く存在していました。KOBUY経由でAmazonを利用可能にする場合、既存のアカウントの取り扱いを考えなければなりません。
大学のメールアドレスで登録しているアカウントを、そのまま大学用として移行して良いのか、それとも個人用を別のメールアドレスに変更し、新たに大学のアカウントを登録するのか、調べていかなければなりませんでした」(杉田さん)
こうしたデータの集約と調査によって、スムーズなAmazon利用の移行作業が進行していきます。
KOBUY経由でのAmazon利用に切り替えることで、利用する教員や研究室の情報が集積され、学内の研究室までの配達へとサービス向上をさせることができるようになります。
しかし、ここでも調査が必要となりました。
杉田さん
「最も苦労したのは、教員や研究室が、学内のどこにあるのか?をとりまとめる調査でした。どの建物の何階に、どの研究室があるのか?というデータを一元的に管理しているデータがなかったのです。そのため、全部署から、研究室の場所の情報を集めなければなりませんでした」(杉田さん)
これらの調査の必要性、物品を購入する教員の手間の低減と購買体験の向上などは、KOBUYカスタマーサクセスを担当する加藤昌孝がすすめてきました。
業務そのものの理解、関連する手続きや申請書類の流れ、また、実際に利用する教員のニーズ、そして杉田さんら学術研究支援部の業務負担低減など、部分だけでなく、全体を見据えた取り組みに、伴走することで、DXの取り組みを行ってきた様子がわかります。
見えてきた、定量的な効果による労働時間削減
近畿大学の学術研究支援部で設定していたKOBUYで目指す指標は、研究費の執行の3割を占める立替精算の削減でした。その数1500件以上、Amazonだけでも年間645件に上り、これらがKOBUY経由での取引に置き換わることがゴールとなります。まだ年度を通した運用の途中であるため、結果はこれからとなりますが、着実に立替は減っているといいます。KOBUY経由への切り替えを拡大していくことを目指しています。
同時に、業務に当たる担当者として、労働効率性の向上を実感していると言います。
杉田さん
「KOBUY以前のAmazon利用は、全て立替精算での利用でした。そのため、毎回立替払い理由書が出てくる状況でした。不備があれば、その都度、追記や問い合わせが発生します。その対応で時間がなくなっていき、業務負担が大きくなっていました。
また、これまで、サプライヤーごとに送られてくる書類のフォーマットが異なっており、チェックすべきところがバラバラになっていました。KOBUYでは、フォーマットが統一され、見るべき箇所が同じであることから、それだけでも作業効率が上がります。特に、年に数回しか利用されないサプライヤーからの書類も、同じフォーマットになっている点はありがたいです」(杉田さん)
今後の更なる業務効率化、自動化を行う上で、フォーマットが同じである点は重要だと、杉田さんは指摘します。
杉田さん
「これまで、研究費を支出する教員は、近畿大学の学内システムに、購入する品物名などをの必要な情報を手入力し、材料用品なのか、新聞図書なのか、購入する種別も入力しなければなりませんでした。それを職員がチェックする仕組みです。
しかしKOBUY導入で書類のフォーマットが揃うことから、ダウンロードした書類を自動で入力するシステムを用意し、教員の手入力の手間を削減することができました。KOBUY経由の書類のフォーマットが揃っていたからこその自動化です」(杉田さん)
KOBUY導入を機に、調達だけでなく、予算管理から支払いまでの業務軽減を目論む近畿大学。現在教員の75%がKOBUYを使いたいとの移行で、今後9割を目指していきたい考えです。近畿大学のDX化の進展に、今後も期待が高まります。