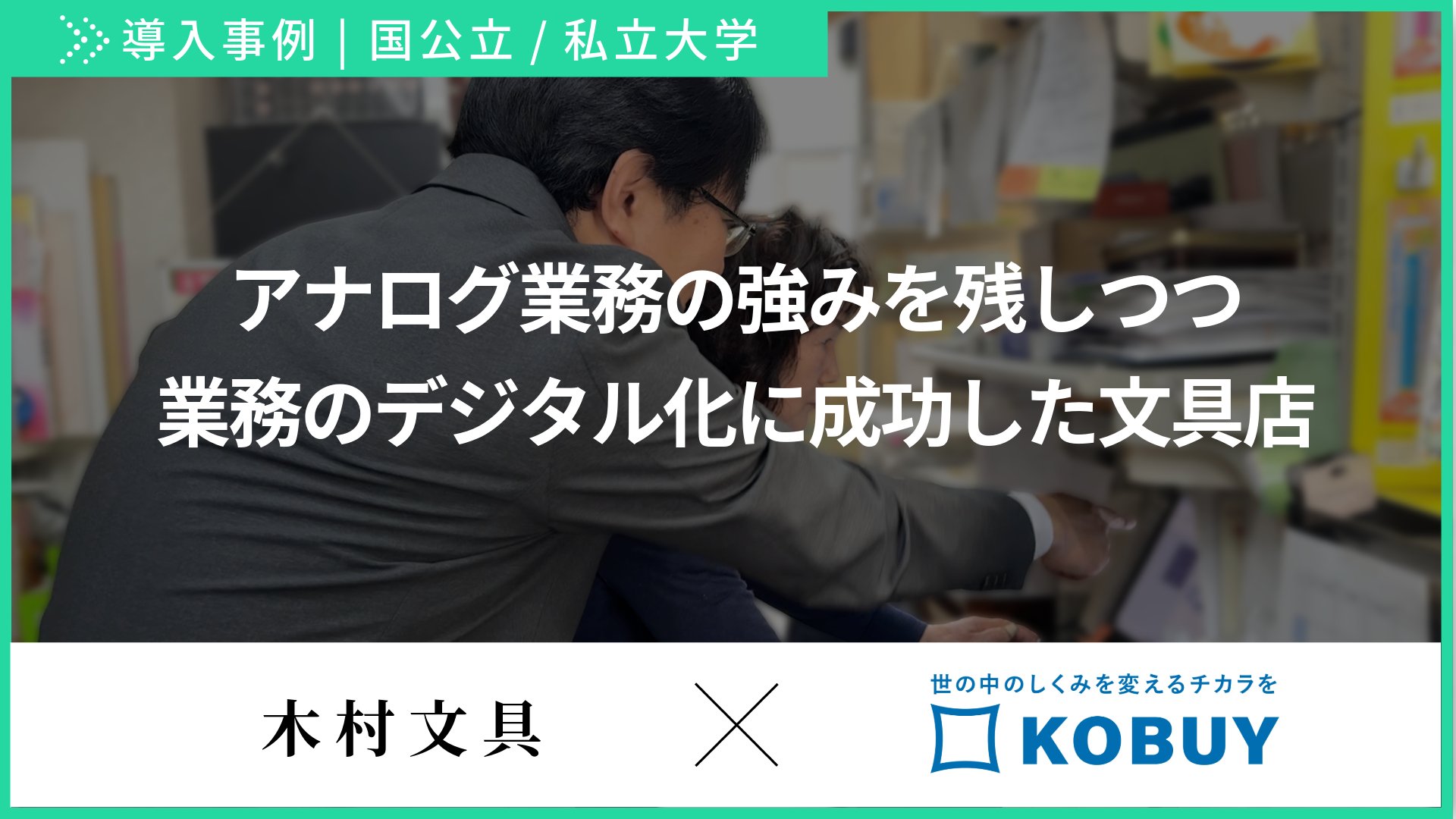【導入事例】木村文具様
木村文具は、25000人以上が通う近畿大学の東大阪キャンパスから、駅に続く商店街に店を構える、文房具屋事務用品の販売店。街の文具屋として親しまれているだけでなく、近畿大学のサプライヤーとしても取引があるお店です。
近畿大学のDX推進に伴い、購買プラットフォームである「KOBUY」を導入することになった際、取引量の多い地元の文具店のデジタル化によるKOBUYへの参画は、近畿大学DXの進捗に、大きな貢献をしています。
木村文具の経営者である福田能之さんに、お話をうかがいました。
木村文具
| 従業員数: | 2人 |
|---|---|
| 事業内容: | 文房具・事務用品 販売 |
インタビュー動画を見る
大学とともに歩んできた、歴史あるお店
木村文具の創業は昭和18年(1943年)。大学の教職員や学生に、文房具や事務用品を販売する、「おなじみのお店」として80年以上親しまれています。
ご自身も近畿大学の出身だという福田能之さんは、木村文具の代表を35年間務めています。その取引について、うかがいました。
福田さん
「大学との取引は、私が代表を務める前から、6枚綴りの伝票に手書きで書いていました。先生のところに行って、顔と顔を合わせて、ご要望を伺って、その場で伝票を書く、という形で注文を取っていました。
先生が必要なものの中には、結構特殊なもの、扱っていない商品もあって、色々な手立てでご用意をして、できる限りご要望にお応えするよう、努めてきました。
ご用意した商品は先生のところに直接お届けしていました。商売と言うよりは、やはり人と人のお付き合い。そうした頑張りと長い付き合いを通じて、先生との信頼関係を築けたのだと思います」
できる限りのご要望にお応えすること、できるだけ早く納品すること、納得のいく価格をお出しすることなど、顔と顔を合わせたビジネスが、木村文具と大学の教員との信頼関係を築く秘訣だった、と福田さんは振り返ります。
変化する取引と時代の流れの中で
そんな木村文具と近畿大学との取引も、時代によって変化がありました。
多くの大学との取引でも同様ですが、大学内の取引のルールが変更されたり、国の資金運用ルールの厳格化への対応が必要になるなど、サプライヤーは大学のルールに合わせていかなければなりません。
木村文具にとっても、近畿大学との取引には変化がつきものでした。その中で大きかった変化は、これまで長らく行われてきた、「顔を合わせて、ご要望を伺い、その場で伝票を書く」という木村文具の受注のスタイルが変わってしまったことでした。
取引の順番と方法がまるっきり変わってしまった、と福田さんは振り返ります。
福田さん
「最初は手書き伝票での受注でスタートしましたが、20年ほど前に、注文の方法は対面からFAXによる発注へと変化しました。さらに、10年ほど前からは、大学は相見積を取らなければ発注ができなくなりました。
発注形態がこれまでの対面からFAX・メールとなり、コミュニケーションよりも価格・納期が重視されるようになっていったのです。対面でのコミュニケーションは納品時に限られ、店舗運営方針の変換を余儀なくされました」
しかし、発注を受けてすぐに商品を直接納品する、という木村文具の良さは、発揮しにくくなります。大学内で相見積を採るため、その手続きに2〜3週間の時間がかかってしまうようになったからです。さらに、変化は続きます。
福田さん
「ただ、受注する前に見積をFAXで出さなければならないため、どうしても価格を下げる競争ばかりになってしまいました。
さらには、検収制度もできて、発注した先生に商品をお持ちする前に、検収室で商品をチェックしてもらう必要がありました」
KOBUY導入に否定的だった
手書きの伝票から始まり、これが20年前にFAXでの発注へ、そして10年前からは見積のやり取りへ。方法が変わりながらも、アナログ取引が続いていた木村文具。ここで、近畿大学からDX推進のため、購買プラットフォームの「KOBUY」導入の話が舞い込みます。
近畿大学は、学内の購買、調達業務をDX化するため、取引をKOBUYの上で実現しようとしました。KOBUYプラットフォームに参画を依頼する企業を厳選、申請件数を重視したため木村文具にもKOBUYへの参画依頼がありました。
木村文具は、これまで大学との取引をIT化しておらず、FAXによる取引をしてきました。その取引をIT化しなければ続けられない、という局面に立たされたのです。
IT化の実現というハードルもありましたが、福田さんはそれ以外にも、ビジネス上の懸念から、KOBUY導入には当初、否定的でした。
福田さん
「システムでの発注に切り替わると聞いて、誰が商品をお届けするのか? これが一番初めに引っかかったところでした。他のオンラインショップと同じように、大学の代表の窓口にしか持って行けないなら、私どもの商売としては、難しいところでした。
お顔が見えない、だから安いところに流れてしまう。商品に関して、コミュニケーションが取れず、先生方が実際にその商品を役立てるところまでお手伝いができない。であれば、何のために私たちの商売があるのか。そう考えて、はじめは否定的な考え方でした」
しかし、福田さんは悩んだ末、最終的にはKOBUY参画を決断しました。
福田さん
「近畿大学は、先進的なシステムや運用をどんどん先駆的に取り入れていく大学。そして世の中の流れもIT化せざるを得ません。
近畿大学との取引を続けるためには、何でもかんでも否定していても、致し方ない話です」
しっかりしたKOBUYの導入・運用サポートに安心
近畿大学との取引を続ける上で、IT化を成功させることが必要だと考え、KOBUY導入を決断した木村文具の福田さん。KOBUYカスタマーサクセスグループのプランナー、加藤昌孝は、近畿大学のKOBUY導入による物品調達に関わるDX推進へ向けた取り組みの中で、木村文具のIT化を強く支援してきました。
加藤のサポートによって、これまでの木村文具におけるFAXを中心としたアナログな取引を、IT化していきました。
福田さん
「木村文具のKOBUY参画に至っては、サポートができているから安心して取り組んでいます。やはりデジタルは苦手なので、システムを使いこなす力量が自分にはなかった。
これだけサポートしてもらえるから、やっても良いなという気持ちになりましたし、実際にやれていると思います」
木村文具がこだわるフェイス・トゥ・フェイスでの取引についても、加藤は大学との調整会議を繰り返します。
その結果、既存取引先が教員に直接納品できる運用を維持したまま、KOBUY導入のメリットを最大限に活かすことができる、発注から納品までの流れを作り上げることができました。教員と「直接コミュニケーションを取る」という木村文具最大の強みを、継続して発揮できるようにしたのです。
「システムは優れているかも知れませんが、技術者は卓上のことしか見ておらず、現場を踏んでいる人は少ないと思います。そのため、現場の動きを知っているカスタマーサクセス担当がしっかりと頑張ってくださり、『ああ、こんな手があったのか』というやり方ができるようになりました」
福田さん
KOBUYの仕組みや使い方、受けた発注の処理の方法、通常と異なる発注の処理の疑問、カスタマーサクセスグループの加藤が、十分にサポートを行うことで、一つずつ解決していきました。
このサポートのおかげで、福田さんはKOBUYを通じた近畿大学との取引に、安心して取り組めるようになり、木村文具は20年間遅れていたIT化を実現することができたのです。
KOBUYによって再評価された
木村文具の「スピードという価値」
近畿大学のKOBUY導入を機に、アナログな受発注を刷新し、IT化を実現した木村文具。KOBUY経由の取引において、木村文具らしさが教員からも評価されているそうです。
福田さん
「システムでの発注で一番問題となるのは、物流です。納品までのスピードは、特に私たちが重視している部分でした。
学校で決裁が下りるまで2〜3週間かかるのが当たり前だったところが、KOBUYに切り替わってからは、納品まで最短で翌日にまで縮まりました。『すごく早いね』と言っていただけて、評価していただいています。
先生方は研究や教育が本分ですので、必要なものがすぐ来ないと困るわけですから」
大学の予算執行の厳格化により、物品申請から発注までに数週間の時間がかかっていた問題が、KOBUYにより解決。そして木村文具は、IT化により、以前提供できていた「迅速な納品」という価値を、再び取り戻すことができました。
長年アナログでのビジネスを続けてきた木村文具。取引先である大学のDX推進の過程で、木村文具もIT化を果たし、KOBUYプラットフォームを通じて近畿大学との取引を継続させています。
KOBUYによって削減された時間は、木村文具ならではの強みだったスピードをより強化し、今日も教員方の研究や教育を支えているのです。